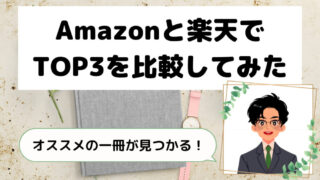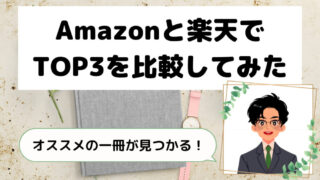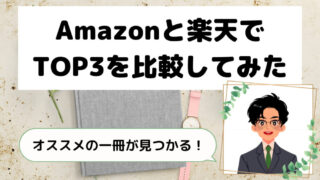こんにちは!
ムコパパです。
このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。
SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」について解説します。
海が抱える問題として、大きく水産物の減少、海洋汚染、海洋酸性化の3つがあります。
- 水産物の減少
- 海洋汚染
- 海洋酸性化
人口増加と魚介類の消費量増加に合わせて、違法な漁業や乱獲が増え、海の資源が減りつつあります。
次に海洋汚染ですが、海洋汚染の話題の中心に上がるのが「プラスチック」です。
プラスチックは自然に分解されず、魚が口にしたり、海の生物に絡まるなどして危害を加えたりしています。
そして海に溶け込む二酸化炭素の量が増えて、海水が酸性に傾きつつあることも問題です。
海は大気の温度と二酸化炭素濃度を調整する役割もしていますが、水質が酸性に傾くと、サンゴの死滅や石灰化に繋がります。
サンゴ礁は海の生き物たちにとって生活の場であり、サンゴの死滅は生態系の喪失を意味します。
真っ白になったサンゴの写真をみたことあるけど、海の酸性化が原因なんだね
今現在食卓を彩っていたり、お寿司を食べに行くと当たり前のように食べられたりする魚介類が、将来食べられなくなる可能性があるのです。
海の豊かさを守るために、この記事では私たちにできる3つの取り組みをご紹介します。
僕は最初はSDGsのことなど全く知らない、ごく普通のサラリーマンでした。
しかし我が子が産まれ、我が子が少しでも住みやすい地球を残したいと思い、SDGsを日々学んでいます。
私たちができることとしては、
- MSC認証・ASC認証マークのついた「サステナブル・シーフード」商品を買う
- マイバックやマイボトルを持ち歩く
- ペットボトルをリサイクルする
の3点があります。
MSC認証とは、「魚を獲りすぎない」「海の生態系に影響を与えない」などの厳しい審査を通過した漁業により獲れた魚介類に与えられる認証のことです。
ASC認証はMSC認証と似ていますが、持続可能な養殖漁業により獲れた魚介類に与えられます。
MSC認証・ASC認証を合わせて「海のエコラベル」といい、それらの認証がついた食材わ「サステナブル・シーフード」といいます。
私たちは普段の買い物でサステナブル・シーフードを買うことで、海の豊かさを守ることになるのです。
このように私たちできる取り組みをしていけば、持続可能な漁業が盛んになり、海の豊かさを守ることができます。
この記事ではそれらをさらに深掘りして解説します。
- 世界の海で起こる問題
- 日本の海の問題
- 私たちにできること
一緒に学んでいきましょう!
- 14.1 2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
- 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
- 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。
- 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
- 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
- 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。
- 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
- 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
- 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
- 14.c 「我々の求める未来」のパラグラフ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。
世界の現状


私たちにさまざまな恵みを与えてくれる海ですが、その海が危険に脅かされているとして世界中で問題視されています。
海が抱える問題として、大きく水産物の減少、海洋汚染、海洋酸性化の3つがあります。
それぞれの問題について説明していきます。
①獲りすぎによる水産資源の減少
第1の問題は、海の資源が減ってしまったことです。
海の資源の減少を招くのは、「違法な漁業」と「人口増加に伴う消費量の増大」です。
漁獲量の増加により、世界の水産資源の状況は次のようになっています。
- 獲りすぎの状態にある資源が34.2%
- 限界まで利用している資源が59.6%
- まだ十分に利用できる資源は6.2%
この先も十分に獲れる資源は6%くらいしかないんだね!
②海洋汚染
第2の問題である海の汚染につながるものが「ごみ」と「排水」です。
特にプラスチックごみが海の生態系に与える影響は深刻です。
プラスチックごみによる汚染と生態系への悪影響
海を汚すごみとして代表的なのがプラスチックごみです。
ごみとなって捨てられたプラスチックごみは、自然に分解されることはなく、そのまま海に行き着きます。
ペットボトルや食品トレーはちゃんとリサイクルに出してるよ?
世界ではまだリサイクルできる施設が整っていない地域もあるんだ。それに加えて「オーシャンバウンドプラスチック」という、海に流れ出る可能性が高いプラごみ予備軍が年々増えているよ
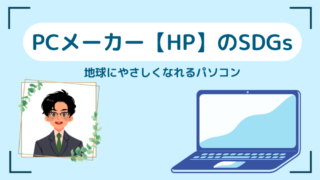
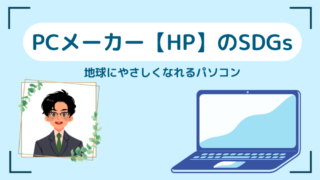
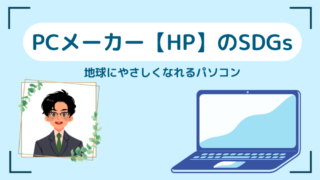
海にたどり着いたプラスチックごみは、海の中で砕けて小さくなります。
小さく砕けたプラスチックを魚や海鳥がエサと間違えて食べてしまい、命を落とすこともあります。
現状のままプラスチックごみが海に流れ込み続けていると、2050年には、海に流れ込んだプラスチックゴミが、海にいる魚の量を超えてしまうといった予想もなされています。
プラスチックゴミはリサイクルするだけでなく、なるべく出さない工夫も必要
処理されない生活排水
発展途上国では生活排水を浄化処理せずに海に排出している割合が高いです。
特に低所得国では8%の水しか浄水処理を施されていません。
上下水道や浄化設備などのインフラを整える資金や技術力が無いことが多いからです。
また発展途上国では、排水を規制する法律や制度がなく、なんの処理もなされないまま汚水を海や川に流すことが一般的であり続けています。
- 途上国では排水が浄化されない割合が高い
- 上下水道や浄化設備のインフラへの資金や技術不足
- 排水に対する規制や法律がない
このようにして世界全体で見ると、生活排水や産業排水の80%が、浄水処理をされないまま川や海に流されています。
③CO2の増加による海の酸性化
海が抱える第3の問題としては、海洋酸性化があります。
海洋酸性化とは、人間の活動によって発生した二酸化炭素を、海が吸収することにより、海の成分が酸性化することを言います。
海洋酸性度は、産業革命以前と比べ、26%上昇しており、2100年までにさらに100%〜150%上昇する見込みです。
海洋酸性化はサンゴの死滅につながる
海洋酸性化によって起こる第1の問題は、サンゴが育たなくなったり死滅してしまうことです。
二酸化炭素が海に溶け込むことで、サンゴの体に必要な炭酸イオンが減少し、サンゴの成長に必要な炭酸カルシウムを作れなくなってしまうからです。
サンゴが死滅すると、サンゴを住みかにしていた生き物が生きる場所がなくなり、多くの海洋生物に影響が広がります。
海の二酸化炭素濃度の上昇は海水温を上昇させる
海は大気の温度や二酸化炭素濃度を調整する役割もあります。
海面と海底の温度差が海流を生み、世界の海洋生物に恵みを与えるのです。
しかし二酸化炭素濃度が増えると、海に熱が蓄えられるようになり、海全体が温まってしまいます。
空気中の二酸化炭素濃度が地球温暖化をもたらすように、海の二酸化炭素濃度も海全体を「温暖化」してしまうのです。
- 海流が乱れる
- 海の生物の死滅
- 氷河が溶ける
- 異常気象や強力な台風を生む
世界の海は海洋汚染と酸性化で大変なことになってるんだね
日本の現状
日本で食べられている魚が将来食べられなくなるって本当?
今のままではマグロが高級魚になって庶民が食べられるなくなると言われているよ
世界人口の増加や漁業の技術進歩によって魚を獲る量が増えていきました。
漁獲量の増加が原因となり、日本人に馴染みのあるマグロやウナギが絶滅の危機にあります。
マグロやウナギの絶滅を阻止するためには、魚など水産物を継続して獲り続けられるような仕組みを考えていく必要があります。
私たちにできること
海の豊かさを守るために、私たちができることは3つあります。
- MSC認証・ASC認証のついた「サステナブル・シーフード」商品を買う
- マイバッグ・マイボトルを持ち歩く
- ペットボトルをリサイクルする
1つ目は、MSC認証マークのある商品を購入することです。
「海のエコラベル」の一つに「MSC認証マーク」があります。MSC認証マークとは、(Marine Stewardship Council:海洋管理協議会)のロゴマークのことです。
海の自然や資源を守りながら獲られた水産物であることを示しています。
MSC認証マークは魚だけではなく、鮭やシーチキンのおにぎりのパッケージにも付けられていることがあります。
魚が使われた食品を購入する時には、このMSC認証マークがついているかどうかを基準にしてみてもいいでしょう。
2つ目はプラスチックごみを出さないように、マイバックやマイボトルを持ち歩くことです。
日本でも、2020年7月からスーパーやコンビニで使うレジ袋が有料化されるようになりました。
カフェなどではプラスチックのストローではなく、紙ストローでの提供も広まっています。
最後に、ペットボトルはリサイクルに出すことです。
資源ごみとして自治体のルールに従ってごみ出しをするか、スーパーなどに設置されている回収ボックスに入れます。
ひとりひとりの心がけが、海の豊かさを守ることにつながるのです。
- 「サステナブル・シーフード」を買うことで水産資源を守ることができる
- プラスチックごみをなるべく出さないことで海に流れ出るごみを減らすことができる
- 海は大気の温度と二酸化炭素の濃度を調整している
最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。
これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!
まずはできることから!
できそうなことから!
SDGsを学ぶには、こちらの書籍がオススメです。小学生でも分かりやすく、大人でも体系的にSDGsを学べます。
この他にもSDGsに関する書籍を紹介しています♪
下記のリンクを是非読んでみてください!