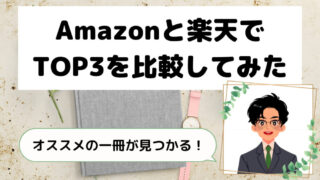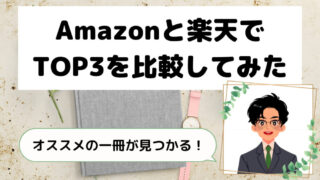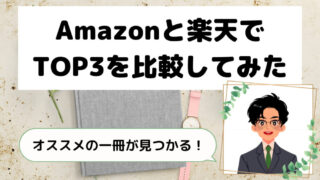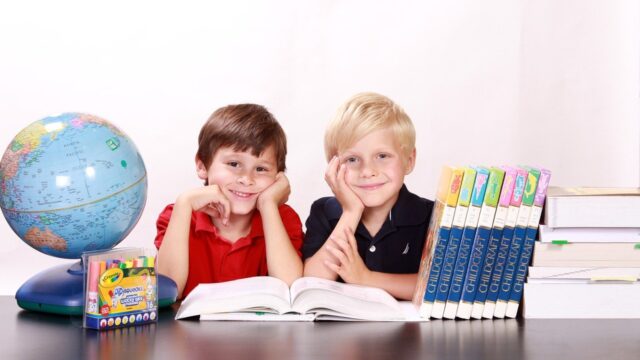こんにちは!
ムコパパです。
このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。
SDGsの目標11は「住み続けられるまちづくりを」です。
持続可能な社会の実現のためには、人々が安心して住み続ける場所が大切なものの一つと数えられています。
しかし世界を見渡せば、近年の人口増加に伴い定住の地をなくしてしまったり、奪われたりする人たちがいます。
それにより世界では大きく3つの問題が起こっています。
- 都市の人口集中に対するインフラ整備の不足
- スラム街の治安悪化
- 大気汚染
大都市に仕事を求めて多くの人が流入している影響で、住む場所を確保できなかったり、定住できたとしても水道やガス、電気などのインフラが足りない状態が生まれています。
また移住してきた人の4人に1人は定職にも就けず、貧困層が集まるスラム街に流れていきます。スラム街は法律が行き届かないケースが多く、治安の悪化を招きます。
そして多くの人が移動すれば、車の排気ガスや公共交通機関の電気使用量などが増えて大気汚染につながります。
どんな人も住めるまちづくりが大切なんだね
人々が定住の地を失うことは、貧困をはじめ様々な問題の発生源となりますが、これは何も世界に限った話ではなく、私たちが住む日本でも大勢の人たちが自分たちの家を失ったりその土地に住めなくなった出来事があります。
「大震災」と、「原子力発電所の爆発による放射能汚染」です。
特に地震後の津波の被害が甚大だった「東日本大震災」では、津波で多くの家々が流されただけでなく、福島原発の爆発により重度の放射能汚染が近隣の市町村を襲いました。
僕もあの事件後に、天気予報と一緒に各地の放射線量の測定値が放送されていたのを覚えています。
福島県の一部ではいまだに放射能汚染が強く残り、帰宅できずにいる地域があります。
震災からの復興に合わせて私たちが考えなければならないのが「さらに災害に対して強靭(レジリエント)な街にする」ことです。
私たちが今住んでいる街をよりよくするために私たちにできることを、この記事で学んでいきましょう。
- 世界で起こっていること
- 日本の「住み続けられなくなった街」に学ぶこと
- 私たちが住む街を強くするためにできること
一緒に学んでいきましょう!
- 11.1 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。
- 11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。
- 11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。
- 11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。
- 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。
- 11.6 2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。
- 11.7 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。
- 11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。
- 11.b 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。
- 11.c 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。
世界の現状【人口増加と人の集中】
都市での暮らしは何かと便利で、生活に欠かせない商業施設・公共施設・学校・交通などが整っており、中心となっています。
その中で現在、問題になっていることを3つご紹介します。
①都市の人口増加にともなうインフラの整備不足
近年の世界人口の55%の人たちが発展した都市で生活をしていますが、今後さらに増え、2050年には70%に上ることが統計学で予測されています。
さらに都市近郊の急激な経済成長によって、農村よりも賃金の高い都市に移り住む人が急増している問題が起こっています。
こうした事態に先んじて改善すべきなのは「インフラ整備」です。
人が増えれば交通機関や日常生活に必要なガス・電気・水道を利用する量も増えます。
そのため、現状的にあらゆるサービスが間に合わない状況が続いています。
また水道管や電線などの老朽化も進んでおり、インフラ拡大の陰で忘れられがちです。
やがて水道管が破裂して街の一部が水没したり、停電に見舞われる可能性もあるのです。
②スラム街の問題
スラム街とは、貧困層の人たちが郊外などの限定的な地域で密集して暮らしている街です。
より良い就業先を求めて移住してきたものの、上手く定着できなかった人たちが集まることでスラム街が形成されるのです。スラム街では法律の手が及ばない地域が多く、犯罪の温床となる場合が多いです。
大都市ではそんなスラム街に4人に1人が住んでいると言われています。
彼らも住みたくてスラム街に住んでいるわけではありません。彼らに必要なのは安定した職業と収入です。そのためにNPOや自治体が中心となり、雇用支援を行っているケースがあります。
具体的には、大工や工芸品の作成などの技術が身につくように支援して、自分たちの手で販売できるようにする活動です。
具体的には、大工や工芸品の作成等技術が身につくように支援して販売できるようにする。
自分たちの力で安定した収入を得ることができるようになれば、スラム街を離れて安全な場所で暮らせるようになることでしょう。
スラム街は貧困にあえぐ人たちが密集して形成された集落。
スラム街は犯罪の温床となり「負の連鎖」を生むため、スラムに住む人たちが自分たちの力で収入を得られるようにする支援活動が行われている。
③大気汚染問題
大都市の人口密度が増えると、自動車の排気ガスやごみの燃焼などによる生活排気が増えることで、局地的に大気が汚染されてしまいます。
そして驚くべきことに、都市に住む90%の人たちが汚染された空気を吸い込んで健康を害しているとされ、肺炎や呼吸不全などにより何百人と命を落としています。
大都市の人口増加による大気汚染問題を解決するためには、電車やバスなど公共交通機関の発達と、エネルギーを再生可能エネルギーにシフトしていく取り組みが必要です。
例えば太陽光や風力などの自然エネルギー由来の電気を利用した電車や、電気の自動車、自転車、バイクなどを利用することで、大気汚染や気候変動の緩和へ繋げることができるでしょう。
大都市では生活排気以外にも、大規模な工場などから排出される有毒ガスが周辺住民の健康を害する【公害】が問題となる場合が多い。
日本の現状【今もなお続く福島県の放射能汚染】
私たちの住む日本でも「住み続けられなくなった街」が存在します。
「東日本大震災」が原因で原子力発電所の建屋が爆発し、漏れた放射能によって汚染された福島県です。
いまだ放射能汚染地域が残っており、徐々に避難指示区域が解除されてはいるものの、10年以上経っても全面解除にはならない現状です。
もともと住んでいた人々は今日も避難先での生活を余儀なくされていますが、いつかふるさとへの帰還を果たすべく、復興が進んでいます。
福島県のうち福島市では市の復興に際し、「福島市SDGs未来都市計画」という計画が現在進行中です。
福島市SDGs未来都市計画の例
「住み続けられるまちづくり」のために福島市が掲げる「福島市SDGs未来都市計画」では、経済・社会・環境の大きく分けて3つの分野で課題を抽出し、それらを解決する取り組みが行われています。
【経済】
課題:「観光などの根強い風評被害、消費や生産活動の縮小の影響で経済の低下傾向」
- 朝ドラ「エール」のレガシーを生かした被災3県連携事業
- 訪日観光客受入環境整備事業
- クリエイティブチャレンジ支援・ビジネスサロン整備事業 など
【環境】
課題:「地球温暖化の影響と推測されている気候変動、自然環境の保全、除染除去土壌の現場保管の早期解消」
- 気候変動対策事業
- 放射線対策事業(除染除去土壌搬出、環境放射量測定事業)
- ゴミ減量大作戦事業 など
【社会】
課題:子育て世代や若者世代等の人口流出、地域におけるまちづくりの担い手の高齢化
- 子育てと教育なら福島市推進事業
- 待機児童対策推進パッケージ
- 地域コミュニティ等支援事業 など
(引用元:福島市役所公式サイト)
福島市に学ぶアクション
福島市の例では、【経済・環境・社会】の3分野で課題を設定していますが、この3本の柱は私たちが住む地域の発展と「住み続けられるまちづくり」に活かせる要素です。
まず経済で私たちにできることは、自分の住む街の魅力を伝えることです。他県や他の市町村の人たちに魅力を発信することができれば、人口流入によって経済効果が得られるでしょう。
環境のうち「気候変動」に関しては私たちでも協力することが可能です。各家庭で再生可能エネルギー由来の電気を供給する電力会社へ乗り換えることで、地球温暖化防止に繋がります。
最後に社会では、地域コミュニティに参加するだけでも役立つのではないでしょうか。高齢者の方だからこそ知っている知識があります。話を聞くことで未来に繋げるヒントがあるかも知れません。
バーの状況が、続いてるのではないでしょうか。
まちを発展させていくためにも、どんな自然災害でも被害が最小限に抑えられ、早い復旧が可能なまちづくりが求められてきます。
私たちにできること
福島市に学ぶアクションを見ると、私たちにできることが浮かんでくるのではないでしょうか。福島市同様、【経済・環境・社会】にわけて考えてみましょう。
【経済】住んでいる街の魅力を発信する
現在自分が住んでいる街の魅力を、SNSを利用して発信してみましょう。
SNSに投降した写真がきっかけで、多くの人が訪れるきっかけになった場所をの例がいくつかあります。
- 出流原弁天池(栃木県)
…Twitterの投稿がきっかけで、「スタジオジブリの作品のような神秘的な光景」が話題となり、多くの人が訪れるようになりました。
地元の方々も、弁天池の魅力を再発見できました。
→https://j-town.net/2020/08/15310103.html?p=all - 通称「モネの池」(岐阜県)
…歴史的画家「モネ」の描いた絵にそっくりだとして話題になった岐阜県の無名の池。
こちらもSNSで人気に火が付いたスポットです。
→https://j-town.net/2022/07/01335934.html
【環境】ごみの処理と資源への配慮
地域によって異なるごみの処理方法をしっかり守ることから、住みよいまちづくりは始まります。曜日やごみの処理方法を守るようにしましょう。
また水や電気などの資源に目を向けてみましょう。特に水は毎年夏になるとダムが枯渇し生活水源が不足する事態が発生します。節水を心がけ、ムダ使いを控えましょう。
- 再生可能エネルギーの電力会社へ乗り換える
- 節水して水資源の枯渇を防ぐ
- ごみ処理方法を守り地域の美化に努める
【社会】地域活動に参加して関係を深める
ごみ拾いや子ども・高齢者への支援活動を通して、地域に住む人たちの顔を確認し合うことで「街の一員」という自覚が芽生えることもあります。
いざというときに住民たちの協力が得られれば、災害に強いまちづくりもできます。避難場所を確認し、災害時に知り合い同士で集まることができれば、先の読めない避難所生活でも不安を和らげることができます。
ローリングストック法で災害時の非常食を備えておく。
食料を多めにキープしておき、少しずつ使いながら買い足すことで「非常食の備蓄」と「賞味期限切れ問題」を同時に解決する災害への準備方法。主に缶詰やレトルト食品などが最適。
- 世界では人口の増加と集中による弊害が起きている
- 「住み続けられるまちづくり」には経済・環境・社会の3本の柱が大切
- 自分の住む地域内でできることからアクションしていく
最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。
これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!
まずはできることから!
できそうなことから!
SDGsを学ぶには、こちらの書籍がオススメです。小学生でも分かりやすく、大人でも体系的にSDGsを学べます。
この他にもSDGsに関する書籍を紹介しています♪
下記のリンクを是非読んでみてください!