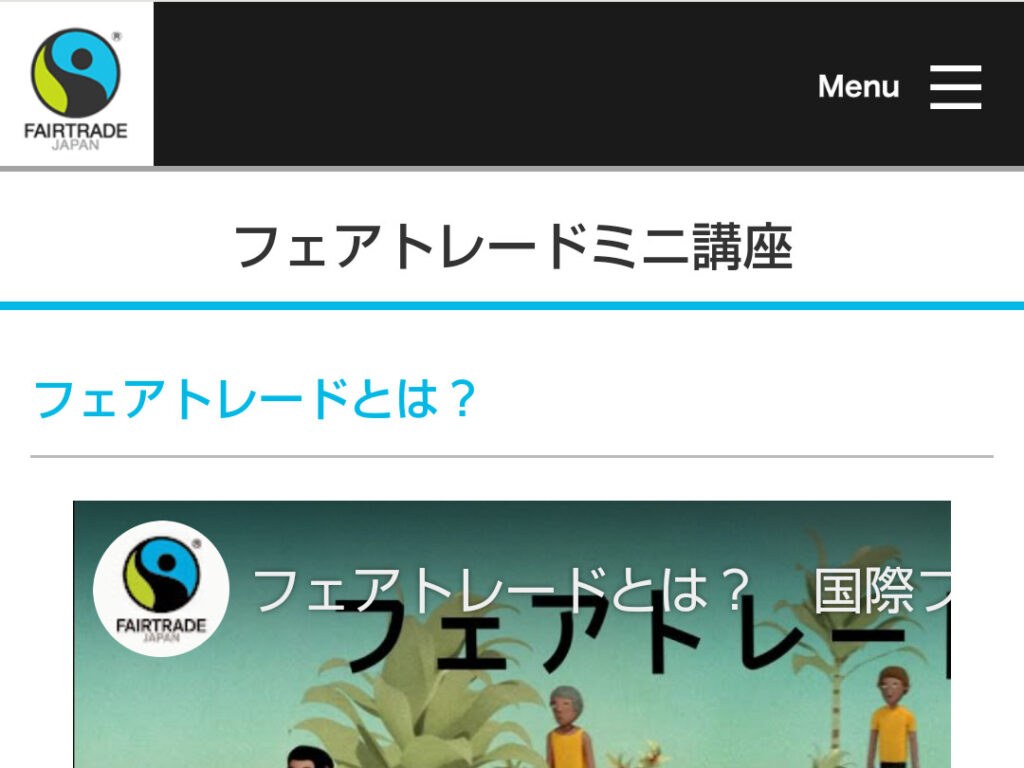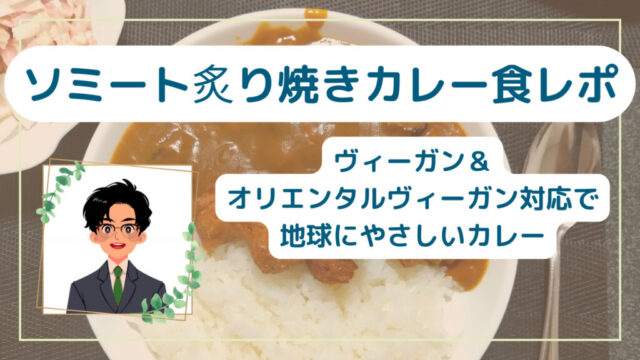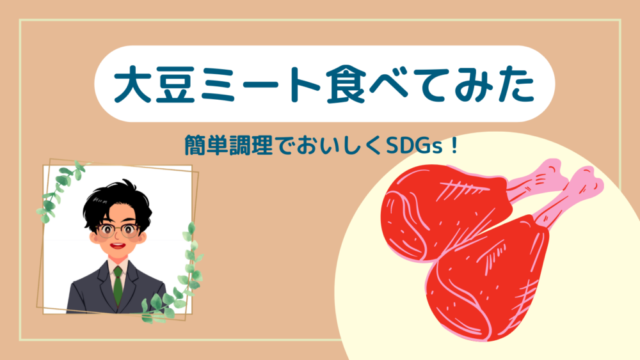- 先進国と途上国の間の不平等問題
- フェアトレードとは?
- フェアトレードを進める活動団体
こんにちは!
ムコパパです。
このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。
日本は食品や石油をはじめ、様々なものを輸入に頼っています。
日本は資源が乏しいため、輸入品がなくては今のような豊かな生活は維持できません。
生活に欠かせないものはもちろん、嗜好品として輸入されているものも多く、私たちは知らず知らずのうちに海外に依存した生活を送っています。
例えばチョコレートの原材料になるカカオは、その多くをガーナという途上国から輸入しています。
しかしガーナのカカオ農家では、少しでも人件費を削減するために子どもが働かされていたり、先進国が不平等な価格でカカオを取引したりといった問題が潜んでいます。
でもチョコレートは食べたいし…どうしたらいいの?
途上国を犠牲にしないためには、【フェアトレード認証】がついた商品を購入することです。
例えばチョコレート製菓の大手である森永製菓では、SDGsが始まる前からカカオの不平等取引や児童労働に目を向け、解決のために活動する団体と協力しあって来ました。
↓おすすめのフェアトレード商品↓

今回の記事では、「フェアトレードについて詳しく知りたい」「誰も犠牲にしないチョコレートを買いたい」という方に向けて、森永製菓の活動内容を解説します。
僕は最初はSDGsのことなど全く知らない、ごく普通のサラリーマンでした。
しかし我が子が産まれ、我が子が少しでも住みやすい地球を残したいと思い、SDGsを日々学んでいます。
一緒に学んでいきましょう!
森永製菓の「1チョコ for 1スマイル」の仕組み


チョコレートの原料には、カカオパウダーが欠かせません。
カカオパウダーはカカオという実の豆から作られますが、カカオが作られる農場は赤道直下の発展途上国に集中しています。
森永製菓の対象商品を購入すると、その売り上げの一部が途上国を応援する支援団体に贈られます。
森永製菓と提携してカカオの生産国を支援する団体は2つ存在します。
「ACE」と「プランインターナショナル」というNGOです。
ACEの活動
ACEは子どもたちを児童労働から守る活動をしているNGOです。
「しあわせへのチョコレート」プロジェクトと題して、チョコの原料であるカカオの生産国の子供たちを支援しています。
児童労働のないチョコレートが当たり前に手に入る社会の実現が、ACEのゴールです。
実は日本は世界で3番目にカカオ豆を輸入している国で、その量は年間28万tにも及びます。
世界で取引されているカカオ豆の量は480万t。
そのうち7割がガーナという赤道直下の途上国で作られています。
そして日本に輸入されるカカオ豆の7割がガーナ産です。
つまり数字の量では、ガーナのカカオ農園で働く子どもは日本と無縁ではない、ということです。
カカオ農園は、ナタや素手を使ってカカオの実を収穫するうえ、大量の重いカカオを運ぶ重労働です。
ガーナでは幼稚園から中学校までは義務教育ですが、一部の貧困家庭では制服や教材を購入できません。
学校に通わせられない家庭を中心に、子どもたちがカカオ農園で働かされているのです。
プランインターナショナルの活動
続いてはプランインターナショナルの活動内容です。
こちらは発展途上国各地の地域の「自立」を目指すNGOです。
先進国が「与え」たり「施し」たりせずとも、現地の子どもたちが主体的に地域開発に参加し、最終的には地域の力だけで問題解決できるようにするのがゴールです。
彼らの活動は、地域の開発を子どもたちと一緒に行うのが特徴です。
なぜなら子どもたちには未来があり、想像力豊かだからです。
どうすればうまくいくのかを話し合い、実行し、解決する力が子どもたちには備わっています。
子どもは国連で定めるところの「子どもの権利条約」によって守られつつ、意見交換と活動を盛んに行い、地域を良くしていく活動に可能な限り参加するのです。
そうやってプランインターナショナルの人材と一緒に成功体験を積ませることで、地域の独立が促されるというわけです。
SDGsのスタート前に実現したフェアトレードチョコレート
子どもたちが危険でつらい目に逢いながら収穫したカカオで作られたチョコを、僕たちは食べていたかもしれないんだ。
それを知っちゃうと、チョコを食べるときに気の毒になっちゃうよね。
けど私たちがたくさんチョコを買えば、ガーナの子どもたちはたくさんお金もらえるんじゃない?
そうでもないみたい。
カカオは貿易で不当に安い価格で先進国に買いはたかれている場合があるらしいよ。
「フェアトレード」っていう認証をきちんと得たチョコを買う必要があるんだ。
フェアトレード認証とは、生産から製造まで全工程にわたって途上国が不利益を被らないように適正価格によって売買されることで途上国の労働を守っているという認証です。
フェアトレードと聞くとSDGsに関連したワードだと思われがちですが、その歴史は第二次世界大戦後にまで遡ります。
アメリカのNGOの女性がプエルトリコ人の作った手芸品を購入したことが始まりだそうで、実に60年以上前のことです。
今でこそフェアトレード専門店などが増えてきましたが、トレード品には品質が伴わないことが多く、商売の種にはなりにくい状態が今でも問題になっています。
そんな中、2014年というSDGsスタート前に森永製菓が実現させたのが国際フェアトレード認証チョコレート「1チョコ for 1スマイル」です。
そのチョコの原料であるカカオは、NGO団体ACEを通じて支援してきた地域で収穫されたものです。
ACEの活動は児童労働の撲滅だけでなく、子どもたちへの教育やカカオ農家の自立を促すなど多岐にわたります。
ACEの活動によって自立したカカオ農家からカカオを仕入れてチョコにする。そこまでの道のりが相当に長かったものであることは想像に難くありません。
「フェアトレード品を買う」というエシカル消費
ここまでは森永製菓と2つのNGOの活動について触れてきました。
フェアトレードを実現させることによって途上国の子どもたちを貧困から救う活動は、一朝一夕では完結しません。
では、私たちにできることは何でしょうか?
それはズバリ、「フェアトレードのものを買う」ということです。
私たち消費者がフェアトレード品を買い、さらに不平等な取引があるという社会問題に目を向けることです。
実は私たちの身近なところに思いもせぬ不平等が潜んでおり、私たちは知らず知らずのうちに不平等に荷担してしまっているかもしれないのです。
その商品が誰の手で作られてどうやってお店に並んだのかを考えて、
作り手のことを想う消費をしよう!
できることから!
できそうなことから!
![]()