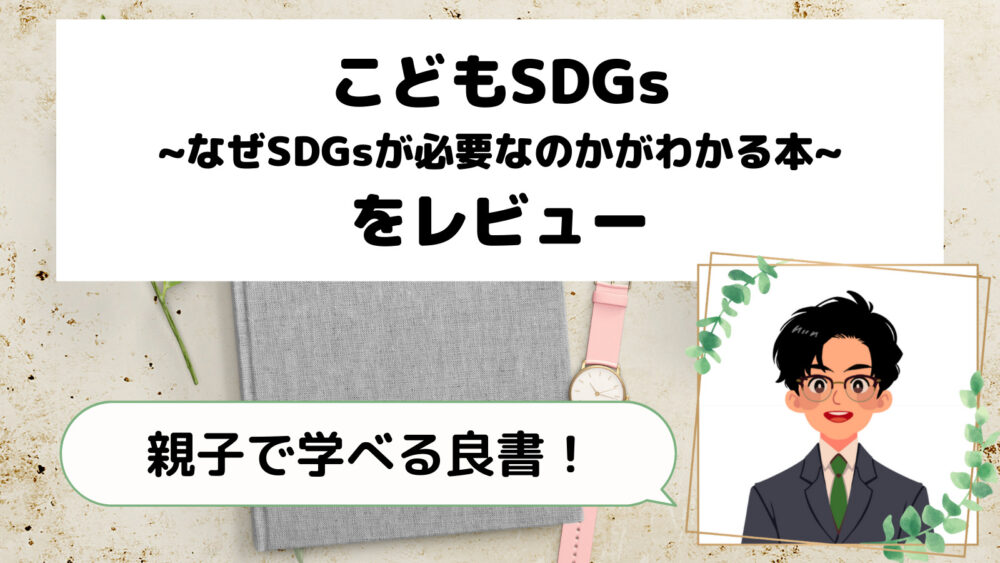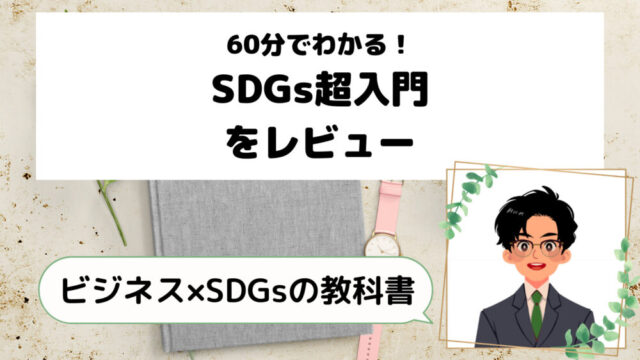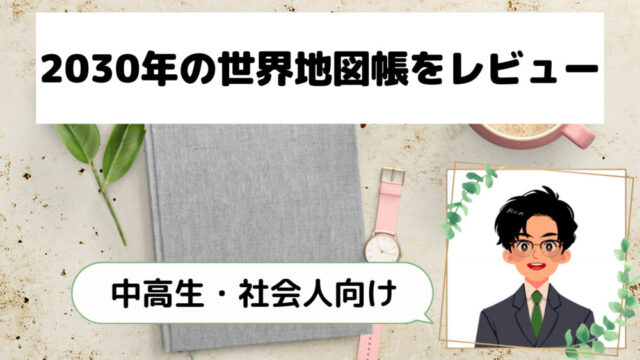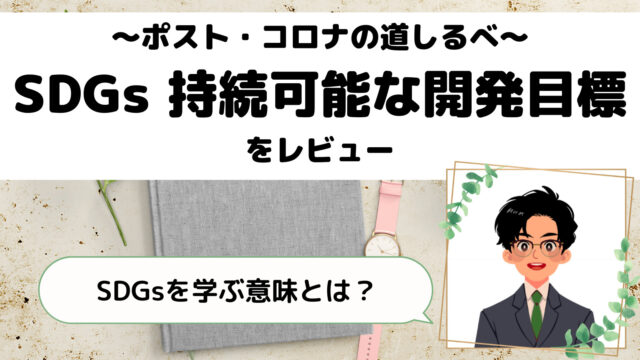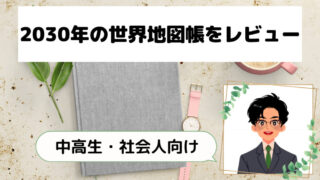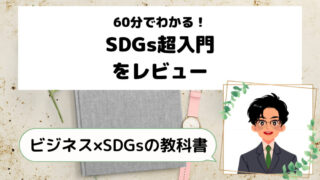- 学校でSDGsについて調べる宿題が出たけど、どうしたらいいかわからない
- 子供からSDGsについて質問されたけど、正直よくわからない
- なんでSDGsが必要なのかよく知らない
こんにちは!
ムコパパです。
このブログではSDGsについて学んで実践できる情報を発信しています。
「SDGsネイティブ」という言葉をご存じでしょうか。
生まれた頃や就学した頃からSDGsに慣れ親しんできた世代の子たちを指す言葉です。
昨今の小学校や幼稚園では、子供たちがSDGsについて盛んに学んでいます。
大人からしたらSDGsは「社会の新しいルール」ですが、子供たちにとってはSDGsは「一般常識」となりつつあります。
社会を回す立場である大人も、遅れをとるわけにはいきません。
ですがSDGsについて調べるのは何となく大変そうですし、どのくらい学べばいいかわかりませんよね。
SDGsについて学ぶなら「本」がもっともオススメです。
本はネットと違って正確な情報が詰まっているため、正しい知識を取り入れるツールとしては最適です。
なかでも一番わかりやすくて一番売れている本なら、安心して学べることでしょう。
大手ECサイトであるAmazonと楽天のどちらでも高評価のレビューを受けているSDGsの関連書籍がコチラです。
「こどもSDGs なぜSDGsが必要なのかがわかる本」です。
こちらの本は子供はもちろん、大人までわかりやすくSDGsを学べる1冊となっています。
- 全ての漢字に読みがなが振ってある
- 見開きでひとつのテーマを説明している
- 写真やグラフが豊富でわかりやすい
読みやすいのはもちろんですが、本書のポイントとなるのは「SDGsを学ぶことで子供が身につけられる力」を説明していることです。
そのためお子さんへのプレゼントなどに適した1冊となっています。
SDGsを通して子供も大人も成長につなげることができる良書ですので、その魅力を解説してきたいと思います。
僕は最初はSDGsのことなど全く知らない、ごく普通のサラリーマンでした。
しかし我が子が産まれ、我が子が少しでも住みやすい地球を残したいと思い、SDGsを日々学んでいます。
- SDGsを学ぶと身につけられる力
- 子供でもできるSDGsアクション
- 親子でSDGsを学ぶ大切さ
一緒に学んでいきましょう!
問題を「自分ごと」として考える力が身につく
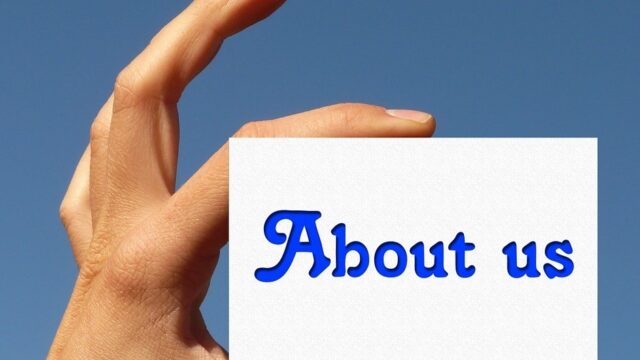
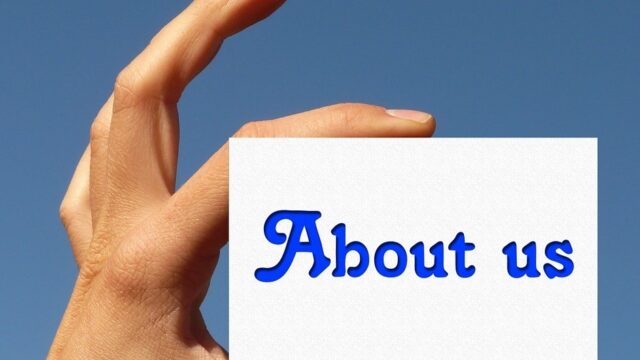
子供向けの本だけど、他のSDGsの本と何が違うの?
子供でも生活の中で世界の問題に触れられることを気づかせてくれる内容になっているよ
本書が結論として述べているのは、「他人事でなく自分事として考える」ことがSDGsの目標を達成するうえで大切な考え方だということです。
なぜならば、世界で起こっている問題と私たちの私生活は無関係ではないからです。
たとえ子供でも、生活の中で世界に目を向ける機会はたくさんあります。自分が普段から食べている食べ物がどこで作られたのか、着ている服がどこで作られたのか、捨てたゴミはどうなるのかなど様々。世界と私たちは、何気ない生活の中で意外とつながっていることに気がつくのです。
世界で起こっている問題も、その原因を追っていくと私たちの生活と結びついています。問題が起こっているのは、他人のせいではなくて「自分ごと」としてとらえれば、問題の解決のために何かできることがあるのではないかと考えることができるのです。
自分ごととして捉えてみよう(例)①「飢餓」問題
世界には食べ物がなくて飢えている人がいるのに、食べ物を捨てている人もいます。食事が満足に摂れず栄養不足に陥っている状態を「飢餓」といいますが、世界には8億2000万人以上の人が飢餓で苦しんでいます。
一方、日本ではまだ食べられる食品が年間612万トンも捨てられています。365日、日本の人口1億3000万人で計算すれば、日本国民が毎日お茶碗1杯分の食べ物を捨てている計算になります。世界では2018年に390万トンの食料が援助されたといいますから、その1.6倍も捨てていることになります。
日本は海外から大量に食料を輸入しているのに、大量の食料を捨てているのが現状です。世界で飢餓に苦しむ人を救うためには、何ができるでしょう。
- 食べ残しをしない
- 残すほど食べ過ぎない
自分ごととして捉えてみよう(例)②「児童労働」問題
チョコレートは好きですか?チョコレートの原料は、カカオという植物の実です。カカオは発展途上国の農場でたくさん育てられていますが、少しでも人件費を下げるために、カカオの収穫に子供たちが働かされている可能性があります。
働かされる子供たちは学校に行けず、学習の機会を逃しています。学習が追い付かなければ、良い仕事に就くことはできません。良い仕事に就けなければ、また安い賃金で働かされてしまい、貧困から抜け出すことが困難になってしまします。そんな子供たちが収穫したカカオで作られたチョコレートを、美味しく食べることができますか?子供たちを負の連鎖から救うためには、何ができるでしょう?
- フェアトレードマークのついたチョコレートを選ぶ



SDGsを学ぶと世界の問題を「自分ごと」として考え、解決のために何ができるかを想像する力が身につく
目標達成のための行動力が身につく


自分ごととして問題を考えても、具体的に何をしたらいいの?
「バックキャスティング」で、目標達成のためにやるべきことを順序立てて計画するんだ
SDGs達成のために重要になるのが、「バックキャスティング」で目標達成までの道筋を立てることです。バックキャスティングとは、目標の実現からさかのぼって今やるべきことを段階的に考えることです。
逆に過去や現在から目標を立てることを「フォアキャスティング」といい、想定された結果しか出せず、期限内により高い目標を達成するには困難となる場合が多いです。
バックキャスティングは、プロスポーツ選手が日々の練習に取り入れていることが多いです。本書では、サッカーで活躍する本田圭佑選手の例が挙げられていました。
本田圭佑選手は小学生のころ「世界一のサッカー選手になる」と決め、何をやるべきかを作文に書いて、本当に実現しました。
- まず、ワールドカップで有名になる
- 外国から呼ばれる
- ヨーロッパのセリエAに入団する
- レギュラーになる
- 10番で活躍する(目標達成)
このように、SDGsの目標達成のためにもバックキャスティングを取り入れれば、一見困難な目標でもそれを実現するために様々なアイデアが浮かびます。
SDGsの目標を達成するためにバックキャスティングで今やるべきことを考え、コツコツと実践することによって行動力が身につく
考え方の違う人と理解し合うことができる


行動に移しても、バカにされたり否定されたりしたらどうしよう
SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を思い出して
考え方の違う人と理解し合う
世界には宗教や主義、常識や価値観の違う人がたくさんいます。互いの考え方を理解し合うことができれば、より良い未来を創造する協力者になることもできます。
逆にお互いを理解し合わずに、一方的に自分の考えをぶつけて衝突してしまうと、紛争や戦争の原因となってしまいます。
そこで重要になるのが「考え方の違う人」とどう向き合うかです。問題解決が自分にとってメリットでも、他の人はデメリットに感じるかもしれません。その際に相手の考えていることを理解し、お互いに納得のいく方法を話し合う必要があります。
SDGsの最後の目標である17個目に「パートナーシップで目標を達成しよう」が設定されているのは、他のあらゆる目標もパートナーシップなしには実現しないからです。
問題を「他人のせい」でなく「自分ごと」として捉えて行動すれば、考え方の違う人と対立しても衝突を避け、どうすれば理解し合えるか考えるきっかけになる
具体的な行動は「ナマケモノにもできるアクションガイド」
以上のとおり、SDGsを学ぶ意義は持続可能な社会を実現するだけでなく、問題を自分ごととして捉えて具体的に行動していける人になるためにもあります。すでに社会人の方でも、一般常識としてだけでなく、想像力と行動力とパートナーシップで仕事をこなしていける人材になるためにもSDGsを学ぶことは有意義と言えます。
その第一歩として本書は「できること・できそうなこと」から行動するとよいと述べられています。具体的には国連広報部より発行されている、誰でも今すぐできるSDGsアクションをまとめた「ナマケモノにもできるアクションガイド」を紹介しています。
詳しくはコチラ↓
https://muko-papa.com/namakemono-1/「こどもSDGs なぜSDGsが必要なのかがわかる本」では、世界で起こっている問題や日本が抱えている課題、SDGs17の目標と169のターゲットについてわかりやすくまとめてあります。ぜひ本書を手に取ってみてください。
見開きで見ると写真やイラストが見やすく読みやすいため、電子書籍よりも紙の本をオススメします。
- SDGsを学ぶことで問題を「自分ごと」として考えることができる
- 問題を「自分ごと」として捉えると、何ができるかを想像する力が身につく
- SDGsの達成のためにバックキャスティングで段階的に目標を立てることで行動力が身につく
- 「他人のせい」より「自分ごと」で考えると、考え方の違う人と理解し合うことができる
最後まで記事を読んでいただき、ありがとうございます。
これからも一緒にSDGsについて学んで行動していきましょう!
まずはできることから!
できそうなことから!